相続人が不在だと財産はどうなる?国庫帰属の仕組みと遺言などの対策を解説

「もし自分に万が一のことがあったら、大切に守ってきた財産はどうなってしまうのだろう…」
お子さまやご兄弟がいらっしゃらない、いわゆる「おひとりさま」の場合、このような不安を感じることもあるかもしれません。
身寄りがない方の遺産は、原則として「国のもの」になります。
しかし、生前の準備次第で、お世話になった方に贈ったり、社会貢献のために役立てたりといった道も拓けます。
本記事では、相続人がいない場合の財産が辿る道のりや、大切な人に遺すための「特別縁故者」の制度、および将来の不安を安心に変えるための生前対策について、わかりやすく解説します。あなたの想いを納得のいく形で次世代に繋げるためのヒントを、一緒に探してみましょう。
- この記事でわかること
-
- 相続人のいない方の財産は、最終的に「国のもの」になる
- 一定の深い絆があった人は「特別縁故者」として遺産を受け取れる可能性がある
- 「遺言書」などの生前対策で、自分の希望を形にできる
相続人が誰もいない財産は最終的に「国のもの」になる
身寄りがない方の財産の行き先は、法律でルールが決められています。まずは、その基本的な流れと、意外と知られていない不動産の特例について見ていきましょう。
民法の規定により相続人不在の遺産は「国庫」へ帰属する
法律(民法959条)により、相続人がおらず、特別縁故者への分与もされなかった財産は、最終的に「国庫」という国の金庫に入ることになっています。
単身の高齢者は増えており、国庫に入る金額も増加傾向にあります。
対象は現金だけでなく、預貯金、家や土地などの不動産、株などの有価証券すべてです。
ただし、亡くなってすぐにパッと国へ移るわけではありません。 家庭裁判所が選んだ「相続財産清算人」が、相続人がいないかどうか調査をし、借金の返済や財産の整理を行います。そのプロセスを経て、最終的に余った分だけが国のものとなります。
不動産が共有名義の場合は「他の共有者」が引き継ぐ
もし、亡くなった方がもっていた不動産が「誰かと一緒に所有しているもの(共有名義)」だった場合は、少しルールが異なります。
相続人のいないその方の持ち分は、最終的には、国ではなく、「一緒に持っている相手(共有者)」のものになります(民法第255条)。
ただし、亡くなってすぐ共有者のモノになるわけではなりません。相続財産清算人が選任されたうえで、遺言により不動産を譲る相手(受遺者)や債権者、特別縁故者への財産の分与が終了したあとで、残余財産があれば共有者へ帰属することになります。
「相続財産清算人」が財産を整理する手続の流れ
相続人がいないからといって、近所の人や知人が勝手に遺品を処分したり口座を解約したりすることはできません。
法的なルールに則って、正しく「遺産のお片付け」をする責任者が必要になります。
家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任申立てを行う
相続人がいることが明らかでない場合、まずは亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続財産清算人」を選んでもらうよう申立てます。
申立てができるのは、お金を貸していた人(債権者)や、亡くなった方のケアをしていた内縁関係にある人など(特別縁故者)の「利害関係人」と、検察官です。 必要書類をそろえたうえで、申立てを行います。
家庭裁判所は、提出された書類を基に審理を行い、適切な相続財産清算人を選任します。相続財産清算人に選任されるために資格は不要です。弁護士や司法書士などの法律専門家が選ばれることもあります。申立人が候補者を示したときは、その候補者が選任されることもあります。
この清算人が、亡くなった方の代わりに「財産の管理・清算をする人」として、手続を進めていくことになります。
選任の申立てには数十万円単位の「予納金」が必要になる
清算人の選任を申立てる際、もし遺産の中から清算人の報酬や経費が賄いきれないと判断されると、「予納金(よのうきん)」というお金を裁判所に預ける必要があります。 金額は財産の規模や複雑さに応じてケースバイケースですが、数十万円から数百万円程度になることが一般的です。
申し立てた人が一時的に立て替える形になりますが、遺産が少ない場合には予納金は戻ってこない可能性もあります。「手続をしたいけれど費用が心配」という方は、事前に資産状況をしっかり調査しておくのが賢明です。
清算人が亡くなった人の債務(借金)や未払金を支払う
清算人は、亡くなった方の財産の管理や保存をし、必要があれば裁判所の許可を得て、不動産や有価証券などを売却します。なかでも借金がある場合は、「マイナスの財産」の整理も大切な仕事になります。
マイナスの財産としては、未払いの税金、未払いの治療費、未払いの公共料金、消費や金融からの借金などがあります。
清算人は官報を通じて、「この方の債権者はいませんか?」と呼びかけます(民法第957条1項。この手続を「公告」といいます)。
名乗り出た人に対して、遺産の中から債権額の割合に従って返済を行います。このプロセスを経て、残りの財産の行き先が決まります。
特別縁故者への財産分与
法律上の相続人がいなくても、生前に深い関わりがあった方には、財産を受け取る権利が認められる場合があります。
内縁の配偶者や献身的に介護をした人は「特別縁故者」になれる可能性
法律上の結婚はしていなくても長年連れ添ったパートナー(内縁の妻・夫)や、親族ではないけれど一生懸命に介護やお世話をしてくれた方は、「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」として認められる可能性があります。
「単に仲がよかった」という段階を超えて、「生計を共にしていた」「家族同然に介護した」などと裁判所に認められれば、清算人が借金の返済をするなどして清算したあとの財産の一部または全部を受け取れる場合があります。
一定の期間内に「分与の申立て」を行う必要がある
特別縁故者として財産を受け取るには、待っているだけではいけません。
相続財産清算人を選任した場合、家庭裁判所は、官報に「相続人がいれば一定の期間内(最低でも6ヵ月)に申し出るように」という内容の公告を行います(民法第952条2項)。
特別縁故者は、この期間が終了してから3ヵ月以内に、家庭裁判所へ財産を分与してほしい旨の申立てをする必要があります(民法第958条の2第2項)。
この期間を過ぎてしまうと、どんなに故人の介護やお世話をしたとしても、特別縁故者として財産分与は受け取れなくなってしまうため注意が必要です。
特別縁故者として裁判所に認めてもらうためには、故人と内縁関係にあったことや、介護の事実を証明するための資料(住民票、写真、日記など)も大切になりますので、早めに準備する必要があるでしょう。
財産を「希望の相手」に遺すための生前対策
「自分の財産は、国ではなく大切なあの人や、応援したい団体のために使ってほしい」。そう願うのであれば、対応できる「今」、法的な準備をしておきましょう。
(1)「遺言書」を作成して特定の個人や団体に寄付(遺贈)する
相続人がいない場合に、亡くなった後の財産を特定の人に譲るために、効果的なのが「遺言書」です。これがあれば、特定の知人や、NPO法人、自治体などに財産を譲る(遺贈といいます)ことができます。
遺言書は書き方のルールが厳しいため、不備で無効にならないよう、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」にするのが安心です。
「母校に寄付したい」「保護猫の活動に役立ててほしい」といったあなたの願いを、確実に形にするために準備しましょう。
(2)「死後事務委任契約」で葬儀や遺品整理の希望を叶える
財産の行き先と同じくらい大切なのが、死後のお片付けです。葬儀、お墓の管理、部屋の片付け、公共料金の解約などを誰にお願いするか決めておくのが「死後事務委任契約」です。
頼れる親族がいない場合、手続を依頼したい人とこの契約を結んでおくことで、あなたの希望通りの供養を行い、周囲に負担をかけずに身の回りを整理してもらうことが可能になるでしょう。
(3)希望を叶えるために弁護士などのアドバイスを受ける
相続人がいる場合、遺言がなくても、法律で相続割合が決まっていますので、基本的にはそれに従って残された人が話し合って遺産を分けることになります。
しかし、相続人がいない場合には、法律で誰にどれだけ分けるか決まっているわけではありませんし、最終的に引き取り手のいない財産は国庫へ帰属します。
「築いた財産を誰に残したい」という希望がおありであれば、弁護士に遺言書作成について相談してみましょう。あなたの希望を踏まえたうえで、具体的な遺言書の文言を提案してもらえます。
まとめ
人生の集大成である財産を、納得のいく形で未来へ繋ぐために、遺言書の作成を検討してみませんか。 相続人がいない財産は最終的に国のものになりますが、しっかりとした準備があれば「お世話になった人」や「社会」のために役立てる道が開けます。
あなたの想いを形にするために、遺言書や死後事務委任契約といった対策は、今から始められる「安心への第一歩」です。
アディーレ法律事務所では、遺言書作成や相続の生前対策に関するご相談を承っております。あなたの財産を納得のいく形で遺すため、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部


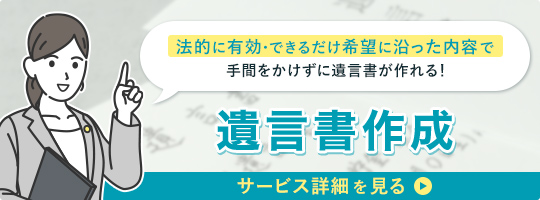


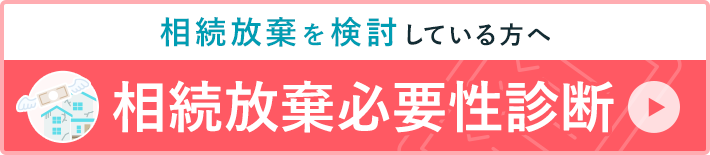

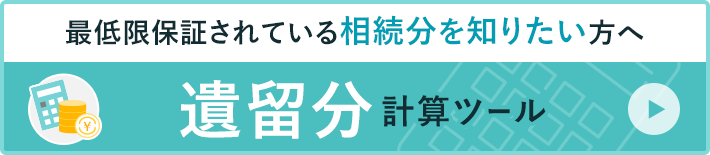



弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。