家族信託の費用の相場はどれくらい?安く抑える方法はある?

家族信託の費用は、最低でも50万円~60万円はかかることが一般的です。
信託する財産や依頼先によっては、100万円以上必要になることもあります。
この記事では、家族信託にかかる費用の詳しい内訳や、財産額別のシミュレーションをご紹介します。
また、自分で手続する場合と、専門家に依頼する場合の違いや、費用を安く抑える方法などもご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
-
- 家族信託の費用相場や詳細な内訳
- 家族信託の費用を誰が支払うか
- 成年後見や遺言との費用の違い
- 目次
家族信託の費用は約50万円~約60万円
家族信託の費用の総額は、一般的に約50万円~約60万円程度が目安です。
具体的な金額は、信託財産の内容や金額、依頼する専門家などによって異なります。
費用は、大きく分けて「信託開始時の初期費用」、「信託中の費用」、「信託終了後の費用」の3段階で発生しますので、それぞれ見ていきましょう。
信託開始時の費用(初期費用)
家族信託を開始する際、初期費用として、主に「専門家への報酬」と「公正証書関係の費用」などがかかります。
専門家への報酬
弁護士や司法書士などに契約書の作成やコンサルティングを依頼する場合の費用です。
目安としては、信託財産の金額の1%前後が目安とされ、最低でも50万円以上かかることが多いです。
公正証書関係の費用
信託契約書は、公的な信頼性を高めるために公正証書にすることが多いです。その際、公証人へ支払う手数料が必要になります。
この手数料は信託財産の価額に応じて定められており、だいたい数万円程度かかります。
詳しく知りたい方は、公証人連合会のWebサイトをご覧ください。
手続に必要な書類の収集費用
専門家や公証人への依頼、金融機関などでの手続ではいくつか書類の提出を求められます。
たとえば、戸籍謄本や印鑑証明書などを取得する場合、合計で数千円程度かかります。
信託口口座の開設費用
信託財産を管理するための口座として「信託口口座」を用意することになります。
口座開設費用として、1万円程度かかることが多いです。
信託中の費用(ランニングコスト)
信託期間中には、たとえば以下のような費用が発生します。
- 信託監督人への報酬
- 受託者への報酬
- 信託不動産の管理費
信託監督人とは、受託者が契約どおりに財産を管理しているかをチェックする役割の人です。
この信託監督人を、客観的な立場である弁護士などの専門家に依頼する場合、その報酬として月に数万円程度かかることがあります。
とはいえ、信託監督人を設置する法的義務などはありません。
信頼できる人が受託者となり、複雑な信託内容でなければ、信託監督人は不要です。
また、親しい家族が受託者になる場合は、わざわざ報酬を求められるケースは多くありません。
信託終了後の費用
信託契約は当初の目的が達成されると終了します。その際の手続や、途中で契約内容を変更する場合に費用が発生することがあります。
たとえば、経済状況の変化などで契約内容を見直すケースが考えられます。
その際は、弁護士などの専門家に変更契約書の作成を依頼するための費用として、数万円から数十万円程度がかかるでしょう。
信託が終了し、残った財産を受取人(帰属権利者)に引き渡したり、信託していた不動産の名義を変更したりする際にも、各種手数料がかかります。
また、終了時の手続も弁護士などに依頼する場合は、その分の費用が発生するでしょう。
信託に伴って支払う税金
家族信託では、信託開始から終了に至るまで、それぞれのタイミングで税金が発生する可能性があります。
具体的には以下のとおりです。
信託開始時
登録免許税(不動産が信託財産に含まれる場合)
登録免許税とは、法務局が管理する登記簿の内容を変更する際に必要となる税金です。
信託によって委託者から受託者へ所有権が移るため、登記簿の内容を変更しなければいけません。
その際、不動産の固定資産税評価額の0.3~0.4%の費用がかかってきます。
贈与税(委託者と受益者が異なる場合)
信託の前後で、信託財産から利益を受ける人が異なるため、委託者から受益者へ贈与があったものとして受益者に贈与税がかかります。
信託中
固定資産税・都市計画税
不動産を信託している場合、納税通知書は名義人である受託者(子など)に届きます。
支払いは信託された財産のなかから行えるよう、契約で定めておくのが一般的です。
所得税、住民税
アパートの家賃収入など、信託財産から利益が生まれた場合、その利益は受益者(親など)のものと見なされます。そのため、受益者が確定申告を行い、所得税や住民税を納める必要があります。
譲渡所得税
信託された不動産や受益権などを売却して、利益が発生した場合は、譲渡所得税という税金が発生します。
信託終了時
登録免許税(不動産が信託財産に含まれる場合)
信託終了に伴い、信託登記の内容を抹消する必要があります。
併せて、不動産の所有権も移転することになるため、法務局への登記が必要になり、登録免許税が発生します。
相続税(受益者死亡による信託終了時)
相続人となる方が信託財産(受益権)を受け継ぐ場合は、ほかの財産と同様に相続税が課税されます。
贈与税(信託財産を第三者が取得する場合)
信託終了によって、今まで受益者だった人以外が信託財産を取得する場合は、その方への贈与があったとみなされ、贈与税が発生します。
【金額別】家族信託の費用シミュレーション
家族信託の費用は、言葉だけではイメージしづらい部分もあります。
具体的な財産状況を想定して、費用の概算がどのくらいになるのか具体的に見ていきましょう。
- ※ なお、以下の例では、委託者と受益者は同一人物であるとし、信託報酬は発生しないものとします。
ケース1:現金5,000万円を信託する場合
現金5,000万円を信託する場合に想定される費用の総額は、約55万円です。
内訳は、以下のとおりです。
専門家への報酬:50万円
5,000万円×1%(報酬利率)=50万円
公正証書関係の費用:約5万円
契約書を公正証書にする際、公証人への手数料が必要になります。
手数料は対象となる財産額によって異なり、詳しくは公証人連合会のWebサイトで確認できます。
5,000万円の場合は、手数料は33,000円です。
また、信託財産の価額が1億円以下の場合、上記の基本手数料に13,000円が加算されます(信託加算)。
その他、証書の枚数に応じた費用が加わります。
手続に必要な書類の収集費用:約1万円
親族や財産状況によって異なりますが、戸籍謄本などの取得費用として、いくらか想定しておく必要があります。
信託口口座の開設費用:1万円
開設費用として1万円を想定します。
ケース2:現金5,000万円と実家を信託する場合
現金5,000万円と実家を信託する場合に想定される費用の総額は、約97万円です。
現金に加えて不動産が含まれる場合、登録免許税と登記手続に関する費用が追加されます。
なお、実家の評価額は建物部分1,000万円、土地1,000万円の合計2,000万円を想定します。
その他内訳は以下のとおりです。
専門家への報酬:85万円
5,000万円(現金)+2,000万円(実家の評価額)=7,000万円
7,000万円(信託財産の評価額合計)×1%(報酬利率)+5万円(信託財産に不動産が含まれる場合の追加費用)=75万円
また信託登記の手続まで依頼するとして、さらに10万円の追加を想定します。
公正証書関係の費用:約6万円
先ほどと同様、財産額に応じた公証人への手数料が必要になります。
信託財産の合計が7,000万円のため、公証人へ支払う手数料は49,000円です。
また、信託財産の価額が1億円以下の場合、上記の基本手数料に13,000円が加算されます(信託加算)。
その他、証書の枚数に応じた費用が加わります。
手続に必要な書類の収集費用:約3,000円
不動産が含まれる場合、評価額を証明できる書類や、登記関係の書類も必要となります。
登録免許税の支払い:7万円
1,000万円×0.4%(建物部分)+1,000万円×0.3%(土地)=7万円
家族信託の費用は誰が支払う?
家族信託の費用は、誰が支払うのか明確に定められているわけではありません。
そのため、信託手続を始める前によく話し合っておく必要があります。
一般的には誰が支払うことが多いのか、タイミングごとに詳しく見ていきましょう。
信託開始時の費用
信託を始める際にかかる初期費用は、信託によって財産管理の利益を受ける「受益者」(多くの場合、財産を託す親)が、信託する財産のなかから支払うケースが多いです。
しかし、状況によっては受託者(子どもなど)が一時的に立て替えて支払うことも可能です。
誰が、どの財産から支払うのかを契約前に家族間で明確に話し合っておきましょう。
また、その合意内容を信託契約書に明記しておくことも大切です。
信託中の費用
信託中に発生する費用は、信託された預貯金から受託者(子など)が直接支払えるように設定しておくのが一般的です。
親(委託者)の判断能力が低下したあとも、子どもが滞りなく支払いを続けられるため、財産管理がスムーズになります。
信託終了後の費用
信託契約が終了すると、残った財産(残余財産)を契約で定められた人(帰属権利者)に引き継ぐための手続が必要です。
そういった手続の費用は、最終的に残った財産のなかから清算して支払う、と定めておくのがスムーズです。
信託契約によって上記のように定めておけば、財産を受け取る人が別途資金を用意する負担がなくなります。
ほかの生前対策との費用比較
生前対策には、家族信託のほかに、「成年後見」や「遺言」といった制度も該当します。
ただしそれらの制度は、目的や役割だけでなく、費用のかかり方も異なっているため、正しく理解しておくことが重要です。
成年後見との比較
家族信託と成年後見の一般的な費用を比較すると以下のとおりです。
家族信託:約50万円~約60万円
成年後見:数千円~数万円
※専門家に依頼せず申し立てた場合。必要書類の数によって変動
成年後見は、最初に必要となる裁判所への申立費用は数万円程度と安価です。
しかし、弁護士などの専門家が後見人に選任されると、月額2万円~6万円程度の報酬が継続的に発生するため、長い目で見ると高額な費用がかかります。
また、申立手続から専門家に依頼すると、さらに数十万円の費用が上乗せされます。
対して家族信託は、初期費用の負担が大きいものの、同居する家族などが受託者となる場合は、その後の運営コストはかからないのが一般的です。
遺言との比較
家族信託と遺言の一般的な費用を比較すると以下のとおりです。
家族信託:約50万円~約60万円
遺言:数千円程度
※自筆証書遺言を作成し、法務局保管制度を利用する場合
遺言は家族信託に比べて圧倒的に安価に作成できます。
自筆証書遺言ではなく、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」だったとしても、作成費用は数万円~十数万円程度なので、家族信託より費用を抑えることが可能です。
ただし、遺言では生前の財産管理に対応していないという大きなデメリットがあります。
たとえば、認知症の親の代わりに不動産を売却するなどはできません。
家族信託であれば、上記のようなケースでも子どもが親に代わって売却することが可能です。
自分で対応する場合と専門家に依頼する場合の費用比較
家族信託の手続は、費用を抑えるためにご自身で行うことも不可能ではありません。
ご自身で手続する場合と各専門家に依頼する場合の費用を比較し、それぞれの特徴についても見ていきます。
自分で手続する場合
ご自身で手続すれば、公正証書作成費用や不動産がある場合の登録免許税といった実費のみで済みます。
専門家への報酬が不要となるため、合計で数十万円ほど節約できるでしょう。
しかし、法律の専門知識なしに作成した契約書には、以下のようにさまざまなリスクが伴います。
- 法的な要件に不備が生じて、信託契約が無効になる
- 内容の曖昧さから親族同士のトラブルに発展する
- 金融機関から信託口口座の開設を断られる
- 税務署から予期せぬ贈与税の支払いを指摘される
司法書士に依頼する場合
司法書士への依頼費用は、信託財産の評価額の1%前後が目安です。
司法書士が主に行うのは、裁判所や法務局などに提出する公的書類の作成です。
また、登記関連の手続も代表的な業務の1つであり、家族信託で必要な「信託登記」も任せることができます。
家族信託に関する手続を一通り任せることができますが、当事者間の揉めごとに発展した場合の対応については難しいです。
親族同士の仲が悪く、トラブルに発展するリスクがあるようなら、弁護士に依頼されたほうがよいでしょう。
弁護士に依頼する場合
弁護士に家族信託を依頼する場合も、同じように信託財産の1%程度が相場です。
ただし、事務所によっては司法書士より高額な報酬体系となる場合もあります。
弁護士の強みは、あらゆる法律トラブルを想定し、その予防策を契約書に盛り込める点です。
また、万が一裁判に発展しても、依頼者の方の代理人として代わりに対応してくれる点もメリットでしょう。
なお、司法書士では原則として紛争の代理人にはなれないため、より安心して家族信託を行いたい方は、弁護士への依頼も検討すべきでしょう。
家族信託の費用に関するよくある質問
費用を安く抑える方法は?
専門家への依頼内容を工夫することで、家族信託の費用を抑えられる可能性があります。
具体的には、以下の2点です。
- 信託する財産を必要最低限に絞る
- シンプルな契約内容にする
専門家への報酬は、信託財産の評価額に応じて決まることが多いため、凍結されると困る資産(たとえば、自宅と一定の預貯金のみ)のみ信託されるとよいでしょう。
また、複雑な信託内容にするとその分対応コストがかかり、費用がかさむ可能性があります。
ただし、費用を抑えることだけを考えると、不十分な信託内容となり本来の目的を達成できないおそれがあるため、十分検討するようにしてください。
信託開始後に契約内容を変えると費用がかかる?
契約内容の変更には、新たに「変更契約書」という書類を作成する必要があり、この書類作成を専門家に依頼する場合、費用が発生します。
内容や依頼先によって異なりますが、数万円から十数万円程度が目安となるでしょう。
また、当初の契約を公正証書で作成した場合、変更契約も同様に公正証書で作成するのが一般的です。その際には、公証役場に支払う手数料も別途必要になります。
家族信託のことならアディーレへ
家族信託の費用は、希望の信託内容や、財産の状況などで大きく変動します。
費用を抑えつつ、効果的な信託契約を締結するには、さまざまな法律知識や経験が必要になるため、一般の方だけでは難しいかもしれません。
アディーレにご依頼いただければ、1人1人のご希望とご家族の状況を丁寧に伺い、紛争リスクを最小限にしつつ、信託設計をサポートします。
家族信託に関するご相談は何度でも無料。概算の費用感や進め方もわかりやすくご案内します。
まずはお気軽にお問合せください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部


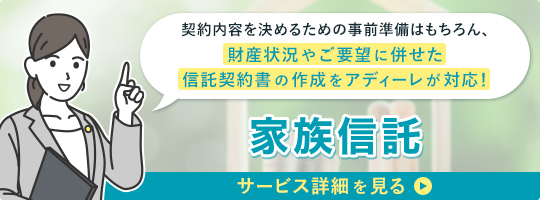
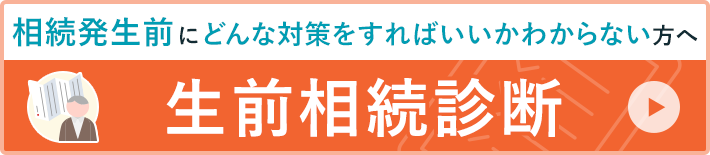

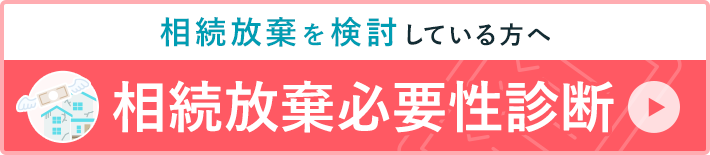





弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。