【弁護士解説】認知症の方が書いた遺言書でも無効になるとは限らない!

認知症の方が書いた遺言書であっても、必ずしも無効になるわけではありません。
というのも、遺言書の有効性を判断するうえで、「認知症かどうか」よりも、重要な判断要素があるからです。
このページでは、遺言書の有効性に大きく関わる「遺言能力」や、遺言書に納得できないときの対処法などについて解説します。
また、認知症の症状が出始めている方に向けて、遺言書を作成する際のポイントもご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
-
- 遺言書の有効性に関わる遺言能力について
- 認知症の方が書いた遺言書に納得できないときの対処法
- 認知症の方が遺言書を作成するときのポイント
- 目次
認知症の方が書いた遺言書でも有効になる場合がある
認知症の方が作成した遺言書でも、法的に有効と認められる場合があります。
というのも、遺言書の有効性について重要なのは、ご本人に「遺言能力」が備わっていたかどうかだからです。
たとえ認知症の症状があったとしても、遺言書を作成した時点で遺言能力があったと認められれば、その方が作成した遺言書は有効と判断される可能性が高いでしょう。
遺言能力とは?
遺言能力とは、ご自身が書く遺言の内容や、遺言によって法的にどのような結果が生じるかを、正しく理解・判断できる能力のことです。
遺言能力に関して、法律による明確な定義はありませんが、たとえば以下のような点が重視されます。
- 自分の財産がどれくらいあるか把握している
- 「誰に」「どんな配分で」相続させるか、自分の意思で決められる
なお、遺言能力とは少し違いますが、法律では遺言ができるのは15歳以上と定められています。
したがって、15歳以上かつ遺言能力のある方であれば、有効な遺言書を作成できることになります。
遺言能力はどうやって判断される?
遺言能力の有無は、さまざまな要素を総合的に考慮したうえで、裁判所によって判断が下されます。
たとえば、認知症の症状が多少見受けられたとしても、普段の会話がしっかりしていて、遺言の内容も合理的である、といった事情があれば、裁判所は遺言能力を認める可能性があります。
以下で、より具体的な判断材料について確認していきましょう。
医学的な検査
医師による診断書や認知機能検査の結果は客観性が高く、遺言能力の判断において重要な証拠として扱われます。
代表的な検査としては、以下の2つが挙げられます。
【長谷川式認知症スケール(HDS-R)】
記憶力や見当識(時間や場所の認識)などに関する質問形式の検査です。30点満点で、20点以下だと認知症の疑いがあるとされます。
【ミニメンタルステート検査(MMSE)】
いくつかの質問を通して、言語能力や図形的能力(空間把握)を簡易的に検査します。30点満点で、23点以下が認知症の疑いの目安です。
もちろん、この検査だけで認知症の断定や遺言能力の判断ができるわけではありません。
あくまで判断材料の1つという点にご注意ください。
本人の言動
本人の普段の言動や生活状況も、遺言能力を判断するための重要な材料となります。
特に、遺言書を作成した時期の前後数ヵ月の状況が重要です。
具体的には、以下のような点が注目されるでしょう。
- 自分の名前や生年月日を正確に言えるか
- 日付や今いる場所を正しく認識できているか
- つじつまの合う会話ができているか
- 自分の財産や家族構成をきちんと理解しているか
- 身の回りのことを自分で管理できていたか
たとえば、遺言書作成の直前に「財産管理について、銀行員としっかりした会話ができていた」といったような事実があれば、判断能力があったと評価されやすくなります。
また、日記や手紙、メールなどからも、当時の状況を判断する証拠として採用されることがあるでしょう。
遺言書の内容
作成された遺言書そのものの内容も、本人の遺言能力を推し量るための判断材料の1つになります。
主に、以下の2つの観点からチェックされます。
【内容の複雑さ】
遺言書の内容があまりに複雑で難解な場合、「本人が本当にこれを理解して作成したのか」と疑問視される可能性があります。
たとえば、「自宅不動産は妻に相続させるが、もし妻が先に亡くなっていた場合は長男に。ただし、長男が相続した場合は、次男に対してその評価額の3分の1を金銭で支払うこと。さらに…」といったような場合が該当します。
【内容の合理性】
なぜその相続分にしたのか、理由が合理的かどうかも見られます。
たとえば、「長年ひどい扱いを受けてきた相手に全財産を渡す」など、不自然な内容になっている場合、本人の正常な判断能力が疑われる一因となるかもしれません。
逆に、作成の動機が「お世話になった長男に感謝を示したい」など、合理的な内容であれば、遺言能力は認められやすくなるでしょう。
遺言能力に関する裁判例
以下は、重度の認知症との診断を受けた女性Aさんが残した遺言書に関して、その有効性が争われた事例です。
【概要】
Aさんは、最初「全財産を原告Bに渡す」という遺言書を残していたが、のちに「全財産を被告Cに渡す」と遺言内容を変更。
原告Bは、「変更後の遺言を作成したとき、Aさんは重度の認知症で遺言能力はなかった」と主張し、遺言の無効を訴えました。
【裁判所の判断】
裁判所は、「Aさんは高度な認知症ではあったが、遺言をするのに十分な能力はあった」と結論付けて、「変更後の遺言は有効」という判決を下しました。
【判決に至ったポイント】
・長谷川式スケールの結果は30点満点のうち4点(高度な認知症に相当)であり、異常行動も見られた
・ただし、入院先の看護師に「かゆいのがましになった」と話すなど、自分の状況を伝えるコミュニケーション能力は保たれていた
・被告Cは、遠い親戚でありながら、長年にわたりAさんを頻繁に訪問し、手厚く面倒を見ていた
・一方、原告側家族は年に数回訪問する程度
・「全財産を被告に遺贈する」という比較的シンプルな内容だった
・遺言書作成時、公証人からの氏名、生年月日、財産内容などの質問に対して明確に回答していた
以上のように、認知症だからといって、一概に遺言能力が否定されるわけではないです。
参考:京都地方裁判所、平成13年10月10日判決、事件番号 :平成12(ワ)2475号
認知症の方が書いた遺言書に納得できないときの対処法
認知症の方が書いた遺言書に納得できない場合、以下の3つの対処法があります。
- 相続人全員での話合い
- 裁判所を通した手続
- 遺留分の請求
具体的には、まず相続人全員で話し合い、それでも解決しなければ裁判所の手続に進むのが一般的です。
以下で詳しく見ていきましょう。
話合いを行う
遺言書の内容に疑問がある場合、まずは相続人全員での話合い(遺産分割協議)を行いましょう。
話合いによって相続人全員で合意できれば、その遺言書の内容に従う必要はありません。
たとえば、遺言書に「次男に全財産を相続させる」と書かれていたとします。
しかし、遺言者である父親に認知症の疑いがあったため、相続人である長男と次男で話し合った結果、「半分ずつに分けよう」と合意できれば、その内容に沿って遺産分割を進めることが可能です。
裁判所を通した手続を行う
話合いで解決しない場合は、裁判所に「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を申し立てて、法的な判断を求めることになります。
【遺言無効確認調停】
遺言無効確認調停とは、裁判官や調停委員を交えて、話合いによる解決を目指す手続です。訴訟と比べて手続が簡易で、非公開のためプライバシーも守られます。
【遺言無効確認訴訟】
遺言無効確認訴訟とは、遺言の有効性についてお互いに主張・立証を行い、その内容に基づいて裁判官が判決を下す手続です。
上記の手続によって、遺言書が無効であると判断されたら、遺言書の内容に従う必要はありません。
遺言書はなかったものとして、相続人同士の話合いによって遺産を分けられるようになります。
遺留分を請求する
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に認められた、最低限の取り分のことです。
遺言書によってこの遺留分が侵害されていないか、確認してみてください。
たとえば、認知症の疑いがあった父親によって、「愛人に全財産を相続させる」という遺言が残されたとしましょう。
残された妻と子が遺言無効確認訴訟をしましたが、結果的に遺言は有効だと認められてしまいました。
この場合、妻と子は、財産をまったく受け取れないわけでなく、愛人に対して遺留分に相当する金額を請求できるのです。
遺留分については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
認知症の方が遺言書を作成する際のポイント
ご自身に認知症の疑いがあり、遺言書の作成に不安を感じていらっしゃる場合は、以下のポイントを押さえながら作成されることをおすすめします。
- 診断書を用意する
- 複雑な遺言内容は避ける
- 公正証書遺言の形式で作成する
- 作成の様子を記録する
- 弁護士に相談・依頼する
上記の点を押さえて作成することで、遺言書の有効性が担保されやすくなり、ご家族間の無用な争いを防ぐことに繋がります。
以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。
診断書を用意する
遺言書を作成する前に、医師から「判断能力に問題がない」旨の診断書を取得しておかれるとよいでしょう。
たとえば、遺言書の作成日と同じ日付の診断書があれば、「作成当時、認知症によって判断能力がなかったはずだ」という主張が出た際に、有効な反証となり得ます。
なお、診断書には、長谷川式認知症スケールのような認知機能検査の結果や、「本人の判断能力に関する具体的な所見」を記載してもらえると、さらに信頼性が高まるでしょう。
複雑な遺言内容は避ける
遺言書に記載する内容は、可能であれば、単純な内容にされることをおすすめします。
遺言の内容が複雑なものになっていると、「この内容を本当に理解して作成したのだろうか?」と、疑われる要因になり兼ねないからです。
特に、以下のような内容は避けた方が賢明です。
- 複数の不動産を、複数の相続人で細かく共有させる
- 「〇〇を条件として、××を相続させる」といった条件を複数設定する
- 特定の相続人にだけ、著しく不公平な内容
一方で、「不動産はすべて妻に、預貯金はすべて長男に」といった簡素な内容であれば、遺言書の有効性を疑われる心配は比較的少ないでしょう。
「公正証書遺言」の形式で作成する
認知症による懸念が少しでもある場合、「公正証書遺言」という形式で作成されたほうがよいでしょう。
公正証書遺言とは、正確な法律知識を持つ公証人に作成してもらう遺言書のことです。
【公正証書遺言のメリット】
・有効性を疑われることが基本的にない
・公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
・相続開始後に、検認(形式面や開封時点の内容を確認する手続)の必要がない
・公証役場保管になるため、破棄・改ざんなどのリスクがない
・「遺言検索システム」を利用できるので、死後に発見してもらいやすい
一方、ご自身で作成する遺言書の形式を「自筆証書遺言」といいます。
自筆証書遺言の場合、公証人などの目が入っていないため、認知症を理由に有効性を疑われるリスクが高くなってしまいます。
また、遺言書の様式の不備で無効になるリスクもあるため、できる限り公正証書遺言を作成するようにしましょう。
公正証書遺言でも無効になることはある?
公正証書遺言が無効と判断されるケースは、例外的に存在します。
公証人が意思能力を確認したにもかかわらず、それを覆すだけの客観的な証拠がある場合には、公正証書遺言であっても無効とされることがあるのです。
たとえば、以下のような状況が考えられます。
- ほかの相続人が作成に不当に干渉しており、本人の意思を歪めていた証拠が見つかった
- 作成時点で、認知症がかなり進行していたことが診断書などから発覚した
とはいえ、自筆証書遺言などに比べて、公正証書遺言のほうが無効になりにくいという事実に変わりはありません。
作成の様子を記録する
遺言書の内容や、その遺言を残す理由などについて、ご自身で話している様子を動画などで記録しておくことも有効です。
動画であれば、文章だけでは伝わらない本人の表情や、声のトーンなどが記録されるため、より説得力のある証拠となるからです。
撮影時は、特に以下の点を意識されるとよいでしょう。
- 撮影年月日がわかるように記録する(当日の新聞を映すなど)
- 撮影者に日付や場所などについて質問してもらい、受け答えの様子を残す
- 「なぜこの遺言を残したいのか」を自分の言葉で話す
なお、動画内で遺言内容について話していても、動画自体が遺言としての効力を持つわけではありませんので、その点はご注意ください。
弁護士に相談・依頼する
認知症の影響を心配されるのであれば、弁護士への相談・依頼も検討されるべきでしょう。
弁護士という「法律の専門家」が遺言書作成に関わることで、遺言の信頼性を高めることができるからです。
またそれだけでなく、以下のようなメリットもあります。
法的に有効な遺言書を作成できる
「遺言能力」についてはもちろん、「遺留分」といった法的に配慮が必要な部分についても、弁護士が代わりに判断をして、適切な内容で遺言書を作成できます。
面倒な手続を任せられる
戸籍謄本をはじめとする必要書類の収集をサポートしてもらえたり、公証人とのやり取りを代わりに行ってもらえたりするなど、各種手続の負担が大きく軽減されます。
遺言執行者になってもらえる
弁護士を遺言執行者(遺言の執行に必要な行為をする権限が認められた人)に指定すれば、遺言内容の実現に向けて尽力してもらえます。
認知症の方が遺言書以外に検討すべきこと
認知症の症状を心配される場合、遺言書の作成以外にも、「成年後見制度」や「家族信託」といった制度の活用も検討すべきです。
以下で、それぞれの特徴についてご説明しますので、併せて検討されることをおすすめします。
成年後見制度
成年後見制度とは、判断能力が不十分になった方の財産や生活を保護するために、裁判所が「後見人」を選任する制度です。
たとえば、悪質な訪問販売で不要な高額商品を買わされた場合、後見人がその契約を取り消し、財産を守ることができます。
また、介護施設に入所するための契約手続など、複雑な法律行為を後見人に任せることも可能です。
ただし、以下のような注意点もあります。
成年後見制度の注意点
- 後見人は裁判所が指定するため、必ずしも希望どおりの人が後見人になるわけではない
- 弁護士などの専門家が後見人になると、継続的な費用が発生する
- 財産をリスクにさらす資産運用(投資)などが、自由にできなくなる
- 制度を途中でやめたり、後見人を自由に選んだり、解任したりすることは難しい
成年後見制度については、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
家族信託
家族信託とは、ご家族に自分の財産の管理や処分を託すための契約です。
家族信託を利用すると、認知症によって判断能力が低下したあとも、柔軟な財産管理を行うことができます。
たとえば、「認知症が進行したら、所有する不動産の管理を長男に任せ、そこから得られる家賃収入は生活費として使い続けたい」といった複雑な内容も実現することができます。
また、成年後見制度では難しい積極的な資産活用も可能です。
ただし、信託契約を結んだご家族が、悪質な契約をあとから取り消したり、契約手続などの法律行為を代行したり、といったことはできません。
遺言書作成のことならアディーレへ
認知症の方の遺言書をめぐる問題は、一概に言えるものではなく、検討すべき点は多岐にわたります。
どうしても遺言書の内容に納得できないという場合は、一度弁護士へご相談されたほうがよいでしょう。
なお、アディーレでは遺言書作成に関するご依頼について積極的に承っています。
ご相談は何度でも無料ですので、ご自身での遺言書作成に不安がある方は、ぜひ一度お気軽にお問合せください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部


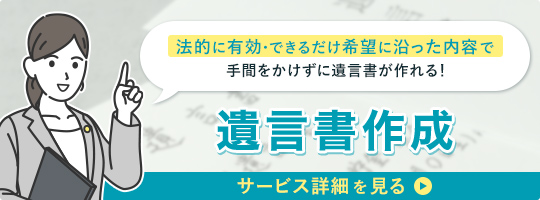
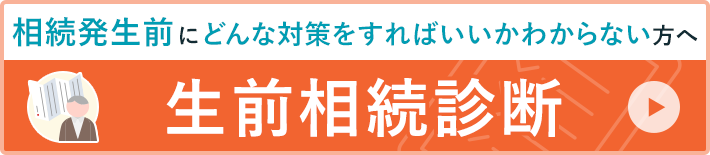

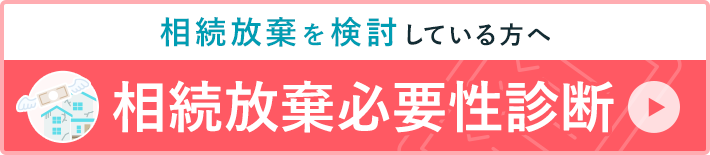





弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。