相続放棄しても訴えられることはある?訴えられたときの対処法は?

相続放棄の手続が完了していても、なかには訴えられるケースがあります。
「相続放棄をしたから、自分にはもう関係ない」といって何もしなかった場合、大きな損害を被るおそれがあるため、適切な対処が必要となります。
このページでは、相続放棄をしたとあとに訴えられたときの対処法をはじめ、「どんなときに訴えられるのか」などについて詳しく解説いたします。
相続放棄を検討されている方も、すでに相続放棄を行った方も、ぜひ参考になさってください。
- この記事でわかること
-
- 相続放棄をしたあとに訴えられるケース
- 相続放棄をしたあとに訴えられたときの対処法
- 訴えられたときに弁護士に依頼するメリット
- 目次
相続放棄をしても訴えられることがある?
結論からいえば、相続放棄の手続を終えても、訴えられることはあり得ます。
具体的には、以下のような場合です。
- 相続放棄をしていないと思われている場合
- 相続放棄の有効性を疑われている場合
- 遺留分を侵害している場合
以下で、詳しく見ていきましょう。
相続放棄をしていないと思われている場合
相続放棄の手続をしても、裁判所や役所などの公的機関が債権者などへ通知することはありません。
そのため、債権者などは、請求対象の相続人が相続放棄したとは知らずに、借金の返済を求めて訴訟を提起してくることがあるのです。
債権者などからの訴えを回避するためには、ご自身が相続放棄をした事実を、あらかじめ債権者に連絡しておくとよいでしょう。
連絡方法や文例については、以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。
相続放棄の有効性を疑われている場合
相続放棄の手続の有効性を疑われて、訴えられるケースもあり得ます。
というのも、裁判所が気づかないところで「単純承認」とみなされる行動をしていた場合、相続放棄が無効になることがあるからです。
単純承認となる例
- 被相続人名義の預金口座を解約してお金を使い込んでいた
- 不動産の売却や名義変更を行っていた
- 被相続人の財産を隠ぺいしていた
上記のような行動をしていた証拠を、仮に債権者が掴んだとしたら、相続放棄の有効性を争ってくる可能性があるでしょう
遺留分を侵害している場合
遺留分とは、各法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。
たとえ相続放棄をしていても、この遺留分を侵害しているとほかの相続人から訴えられる可能性があります。
よくあるケースとしては、被相続人が存命のうちに、多額の生前贈与を受けていた場合です。
たとえば、以下のような例をもとに考えてみましょう。
被相続人:父
法定相続人:長男、次男、三男
生前贈与:長男にだけ500万円(相続開始10ヵ月前に贈与)
相続財産:100万円
相続放棄者:長男のみ
相続割合:次男と三男で2分の1ずつ
上記の場合、次男と三男の遺留分を計算するときには、法律上、長男が受け取った500万円を加えることになります。
次男と三男には、算出された遺留分に満たない金額分を、長男に請求する権利があるのです。
ただし、遺留分の計算は非常に複雑です。詳しくは以下のページで解説していますので、併せてご覧ください。
相続放棄したのに訴えられたらどうする?
万が一、相続放棄後に訴状が届いても、絶対に無視してはいけません。
「手続は完了しているから大丈夫」と考えて無視していると、思わぬ損害を被るおそれがあります。
以下でご説明する対応を速やかに行うようにしましょう。
すぐに状況を確認する
まずは届いた訴状や書面の内容を確認しましょう。
たとえば、以下のような内容は特に重要となりますので、必ず確認してください。
- 誰が訴えてきたのか(債権者か、ほかの相続人なのか)
- なぜ訴えられたのか(請求の趣旨や原因)
- 何を要求されているのか(お金や不動産、権利など)
- 反論書(答弁書)の提出期限はいつか
- 裁判の期日はいつか
上記の情報をもとに、今後の対応を検討することになります。
相続放棄申述受理通知書を提出する
あなたが相続放棄をした事実を、相手が知らないようなケースであれば、「相続放棄申述受理通知書」を提出するだけで解決できるかもしれません。
相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の手続が裁判所によって受理されたことを公的に証明する書類です。
この書類のコピーを提出することで、支払義務がないことを主張できます。
仮に通知書が手元にない場合は、裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらいましょう。この証明書も通知書と同様の効力を持ちます。
答弁書の作成・提出をする
訴状によって訴えられた内容に対して、反論や意思表示を行うために作成・提出するのが「答弁書」です。
答弁書には、たとえば以下の内容を記載します。
- 訴えを取り下げてほしいこと(原告の請求を棄却すること)
- 相続放棄を行ったため支払義務がないこと
- 受理された相続放棄の事件番号や受理日
ただし、法律の知識や豊富な経験がなければ、効果的な答弁書を作成するのは困難です。
少しでも不安がある方は、このあとご説明するように弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
弁護士に相談する
弁護士に相談をすれば、効果的な答弁書の作成から裁判所とのやり取り、相手方との交渉まで、さまざまな手続を任せられます。
特に、相続放棄の有効性を疑われていたり、遺留分侵害額請求をされていたりする場合、複雑な法律知識が必要になることが多いため、弁護士にご相談・ご依頼されたほうがよいでしょう。
そのほか具体的なメリットについては、のちほど詳しくご説明いたします。
相続放棄後に訴えられたときのよくある疑問
慌てて借金を支払ってしまったらどうなる?
支払ったお金を取り戻すことは、難しいと言わざるを得ません。
というのも、その支払いは「第三者弁済」という、法的に有効な返済とみなされる可能性が高いからです。
第三者弁済とは、本来の債務者に代わって、ほかの人が借金を返済することを指します。
事情を説明して、債権者が返金に応じてくれるのであれば別ですが、断られた場合はそれ以上請求できません。
ただし、場合によってはお金を取り戻せる場合もあります。詳しく以下のページをご覧ください。
市役所からの請求は支払うべき?
市役所などからの請求については、基本的には支払うべきといえます。
たとえば固定資産税であれば、その年の1月1日時点の登記簿や固定資産課税台帳上の所有者に課税されて、正式に納税義務が発生している可能性があるからです。
【相続放棄をしたのに、納税義務が発生している例】
被相続人:父親A
法定相続人:長男B(配偶者はすでに死別)
相続財産:預貯金、実家(家屋、敷地)
11月1日
Aが亡くなり、相続が発生。Bは相続放棄の手続を始める
↓
(翌年)1月1日
固定資産税が課税される(課税基準日)
↓
2月20日
Bの相続放棄が受理される
↓
4月10日
B宛てに固定資産税の請求書が届く
対応方法として、市区町村へ不服申立てを行ったり、最終的に相続人となった人へ支払った分を請求したりすることが挙げられますが、確実にお金が戻ってくるとは限りません。
手続に際して年をまたぐ可能性などがあれば、念のため弁護士に相談されたほうがよいでしょう。
「連帯保証人」としての返済を求められたら?
相続人である方が被相続人の連帯保証人であった場合、相続放棄をしても、連帯保証人としての返済義務はなくなりません。
相続放棄に免除されるのは、被相続人が抱えていた借金の返済義務だからです。
たとえば、父親に500万への借金があり、唯一の相続人である息子が相続放棄した場合を考えてみましょう。
①息子が連帯保証人ではなかった場合
相続人としても、連帯保証人としても返済義務はない
②息子が連帯保証人だった場合
相続人としての返済義務はないが、連帯保証人としての返済義務がある
相続放棄後に訴えられたときに弁護士に相談するメリット
相続放棄をしたあとに訴えられた場合は、やはり弁護士に相談されることをおすすめします。
裁判所が関係する事態になった時点で、一般の方だけで対応するのは非常に負担が大きいからです。
訴えられたあとの対応を弁護士に依頼した場合、たとえば以下のようなメリットがあります。
【答弁書などの書面を作成してもらえる】
自分で作成する手間がなくなるだけでなく、より適切な内容の書面を作成できるため、その後の手続がスムーズに進む可能性が高くなる
【適切な対応や反論をしてもらえる】
正確な法律知識や豊富な経験をもとに、裁判対応や相手方への反論をしてもらえるため、自分で対応するより問題が解決しやすい
【精神的な負担が軽減される】
債権者・ほかの相続人とのやり取りや、裁判手続を任せられるので、精神的な負担が軽減される
相続放棄の手続をするならアディーレへ
ご説明したように、相続放棄後に訴えられる理由はさまざまです。
訴えられた理由に応じて適切な対応が必要になりますが、状況によっては、一般の方だけでは難しい
場合もあります。
少しでも不安があれば、すぐに弁護士へご相談されたほうがよいでしょう。
なお、アディーレではこれから相続放棄をする方のご依頼を積極的に承っております。
アディーレにご依頼いただいて相続放棄をされた場合は、相債権者への対応もアディーレが行います。
相続に詳しい弁護士が、あなたに代わって相続放棄の事実や有効性などを主張しますので、万が一訴えられた場合も心配する必要がありません。
ご相談は何度でも無料ですので、相続放棄をお考えの方はぜひお問合せください。

- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部


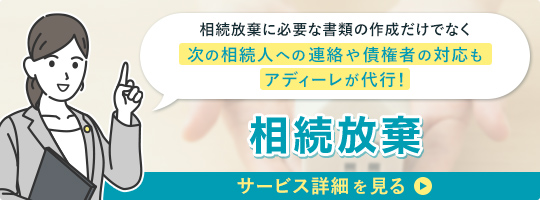
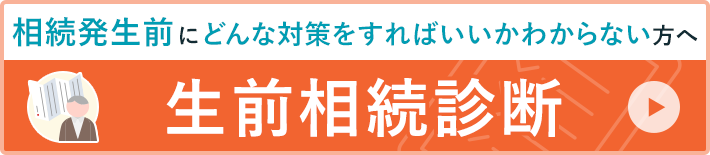

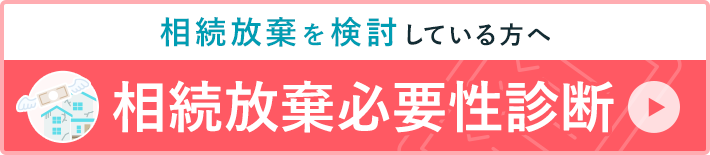





弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。